|
2026/02/17 07:17
|
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
2023/04/07 16:29
|
|
ペンタトニックスケールや琉球音階、ブルーススケールなど、スケールを使ったメロディー作りはおススメではありますが、初心者の方には少し難しく感じるかもしれません。 特に、伴奏のコード進行に合わせてペンタトニックスケールなどの音階を使う場合には、コード進行の各コードの構成音と、ペンタトニックスケールの始まりの音が非和声音になってしまうこともあるので、不協和音にならないようにする工夫が必要になります。 ですので、初心者の方にも簡単に出来るメロディーの作り方としてお勧めしたいのは、ダイアトニックスケールを使ってメロディーを作る方法です。 ダイアトニックスケールとは?ダイアトニックスケールとは、楽曲の調の主音から始まる自然長音階、または自然短音階の7つの音を始まりの音として、その楽曲の主音から始まる自然長音階、または自然短音階の7つの音だけを使って作る7音で構成された音階の事です。 文章だと分かりづらいかもしれませんが、ダイアトニックスケールはピアノの鍵盤や五線譜で見るととても簡単なスケールです。 例えば、「ハ長調」の楽曲では、主音は「ド」であり、「ド」から始まる自然長音階は「ドレミファソラシド」となります。 「ハ長調」におけるダイアトニックスケールは、この「ドレミファソラシド」の7つの各音を音階の始まりの音として、この7つの音だけを使って7音構成の音階を作ります。 ですので、「レ」を始まりの音として「レミファソラシド」、「ミ」を始まりの音として「ミファソラシドレ」といった感じでダイアトニックスケールが作られます。 また、ダイアトニックスケールは、その楽曲の調の主音から始まる自然長音階の何番目の音を始まりの音にしているかによって名称が付けられています。
コードの構成音と協和音になる音から始めるメロディーにするメロディーの歌いだしが、コードの構成音と不協和音になる音の場合、メロディーの響きが弱く感じますし、ボーカルの人も歌いづらいのではないかと思います。 ですので、コードを鳴らすのと一緒にメロディーの歌いだしが小節の1拍目表から始まる場合などには、ほぼ必ず、コードの構成音とメロディーの歌いだしの音が協和音になるようにメロディーが作られます。 ただ、伴奏というのは複数のコードが組み合わさったコード進行によって作られるので、コード進行の各コードにおける構成音になるようにメロディーの始まりの音を決める必要があります。 そうした時に利用すると良いのが、ダイアトニックスケールです。 ダイアトニックスケールは、その楽曲の調で使う音だけで作られつつ、その楽曲の調で使う7つの音全てから始まる7種類のスケールとなっています。 ですので、コード進行の各コードの構成音に当てはまる音が、始まりの音となっているダイアトニックスケールが必ずあるので、もし、メロディー作りに行き詰まったりした場合には、ダイアトニックスケールを使ってみましょう。 にほんブログ村 PR |
|
2023/04/02 15:35
|
|
メロディーの作り方としてお勧めなのが、スケール(音階)を使った作り方です。 以前の記事でも説明しましたが、スケールというのは1オクターブの範囲で階段状に音が並んでいる状態の事です。 スケールを使う際に、楽曲の調で使うと定めている音を使ってメロディーを作ると、基本的には、その楽曲のダイアトニックコードと響きが噛み合うメロディーが作れます。 楽曲の主音を各スケールの始まりの音にする楽曲の調で定めている音を使ったスケールでメロディーを作る場合には、その楽曲の調における「主音」をスケールの始まりの音にします。 例えば、楽曲の調が「ハ長調」という場合に、メジャーペンタトニックスケールを使ってメロディーを作る際は、「ハ長調」の主音である「ド」の音をメジャーペンタトニックスケールの始まりの音にします。 そうする事で、そのメジャーペンタトニックスケールで使う音が、「ハ長調」で使う音で構成された音になるので、「ハ長調」のダイアトニックコードで作られているコード進行の伴奏に奇麗に噛み合うメロディーになります。 ペンタトニックスケールって何?ブルースやロック、J-POPといったジャンルで頻繁に使われているスケールに「ペンタトニックスケール」というスケールが有ります。 ペンタトニックスケールというのは、1オクターブの範囲において5つの音だけ使って階段状に並べた「五音音階」というスケールの一種です。 ペンタトニックスケールには、メジャーペンタトニックスケールとマイナーペンタトニックスケールがあります。 メジャーペンタトニックスケールは、自然長音階から第四音と第七音を抜いた状態の5音で作られるスケールの事で、マイナーペンタトニックスケールは、自然短音階から第二音と第六音を抜いた状態の5音で作られるスケールの事です。 メジャーとマイナーで使い分けるメジャーペンタトニックスケールを使ってメロディーを作る際には、長調における主音をメジャーペンタトニックスケールの始まりの音として使用する事で、そのメジャーペンタトニックスケールの音は、その長調で定めている音だけを使って構成されます。 ですが、短調における主音をメジャーペンタトニックスケールの始まりの音として使用した場合、そのメジャーペンタトニックスケールの音には、その単調で定めている音以外の音も使われてしまうことになります。 そうなってしまうと、調性が崩れてしまい、その単調のダイアトニックコードと、メロディーのハーモニーが不協和音になってしまいます。 ですので、長調の時はメジャーペンタトニックスケール、短調の時はマイナーペンタトニックスケールというように使い分けてメロディーを作るようにしましょう。 ※ ただ、平行調の仕組みを使えば、メジャーペンタトニックスケールを短調の楽曲の中でも使う事が出来るので、そのことについては別の記事で紹介していきたいと思います。 にほんブログ村 |
|
忍者ブログ [PR] |






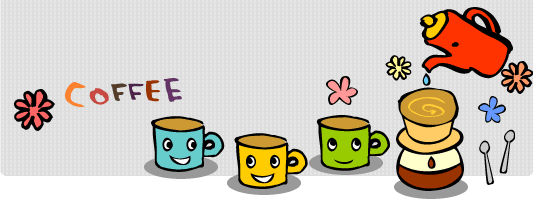
 CATEGORY [
CATEGORY [ 