|
2026/02/17 08:46
|
|
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
|
2023/04/01 18:50
|
|
前回の記事では、メロディーは楽曲で使う音を定めた「調性」の仕組みの中で作られるという事について説明しました。 ですが、実際には、メロディーだけでなく、楽曲の伴奏やフレーズなども「調性」によって定められた音で作られています。 ですので、伴奏で用いられるコード進行の各コードにおいても、「調性」の仕組みにそった構成音でコードが作られています。 こうした「調性」の仕組みの中で使われるコードの事を、一般的には「ダイアトニックコード」と言います。 ダイアトニックコードとは?ダイアトニックコードというのは、楽曲の「調」における主音から始まる自然長音階、または自然短音階の音をコードの根音として、その楽曲の調で使う音を三度音程で積み重ねて作られるコード群の事です。 例えば、楽曲の調が「ハ長調」の場合には、主音は「ハ」(ド)であり、長調なので、「ド」から始まる自然長音階の「ドレミファソラシ」という7つの音をコードの根音として、「ドレミファソラシ」の音だけを三度音程で積み重ねて作るコード群が、「ハ長調」における「ダイアトニックコード」になります。 この五線譜を見て頂いても分かるように、「ハ長調」で使う音だけで全てのコードが構成されています。 そして、基本的には、「ハ長調」の楽曲で使うコード進行における各コードは、このダイアトニックコードの中のいずれかのコードとなっています。 「ハ長調」のコード進行パターン「ハ長調」のコード進行パターンで代表的なものには以下のものがあります。
この他にもハ長調のコード進行パターンは色々ありますが、どんなコード進行であっても、ハ長調の場合には、先ほど紹介したハ長調のダイアトニックコードのコードが使われています。 もちろん、丸の内サディスティック進行と呼ばれるコード進行のように、途中で「ハ長調」以外の音を入れる事で、部分転調による不安定な雰囲気を作り出すコード進行もあります。 ただ、そうしたコード進行も、基本的には、ダイアトニックコードを元にコード進行が構成されているので、メロディーの作り方の知識と合わせて、コード進行における「調性」の知識も覚えておくと、作曲がしやすくなると思います。 にほんブログ村 PR |
|
2023/03/26 18:15
|
|
メロディーの作り方には色々なパターンがありますが、鼻歌やスケール、コード進行に合わせる、といった、どんなメロディーの作り方をするにしても、必ず「調性」という音楽理論の知識が不可欠になります。 また、メロディーだけでなく、伴奏のコード進行、ギターやバイオリンのフレーズなど、ドラムのように噪音を使ったパートではなく、ピアノやギター、バイオリンのように音程のある楽音を使ったパートを作る際にも、必ず「調性」についての知識が必要になります。 ですので、今回は、音楽理論でとても重要な「調性」についての知識について説明していきたいと思います。 「調性」とは?「調性」(ちょうせい)というのは、楽曲の中で使う音(音名)を定めるための仕組みの事を意味しています。 例えば、楽曲の「調」が「ハ長調」という場合には、”楽曲の中で「ドレミファソラシド」の音を使う”、という事になります。 もちろん、転調や部分転調を行う楽曲では、「ハ長調」であっても、「ド#」や「ミ♭」といった音を使ったりもしますが、「ハ長調」の楽曲では、ほとんどの場合、コード進行のコードも、メロディーやフレーズも、「ドレミファソラシド」の音で作られています。 「ハ長調」が示している事「ハ長調」というのは、”「ハ」(ド)の音から始まる「自然長音階」(ナチュラルメジャースケール)の音を楽曲で使います。”、という事を示すためのものです。 「調」には「短調」もありますが、「調」が「短調」という場合には、付いている文字を始まりの音として、「自然短音階」(ナチュラルマイナースケール)の音を楽曲で使います。”、という事を島しています。 短調の一つに「ヘ短調」(Key : F minor)などがありますが、ヘ短調の場合には、「へ」(ファ)から始まる自然短音階の音を楽曲の中で使う事になるので、「ファソラ♭シ♭ドレ♭ミ♭ファ」という音を使ってメロディーを作る事になります。 また、「ニ長調」という場合には、「二」(レ)から始まる自然長音階の音を使うので、「ニ長調」の楽曲では、メロディーを作る際に「レミファ#ソラシド#レ」の音を使います。 このように、メロディーを作る際には、「調性」によって定められている音を使う事で、初心者の人であっても、メロディーが簡単に作れるようになります。 ですので、メロディーの作り方を覚えたいなら、まずは、「調性」についての知識を覚えておきましょう。 にほんブログ村 |
|
忍者ブログ [PR] |






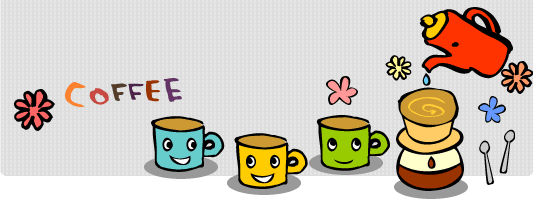
 CATEGORY [
CATEGORY [ 